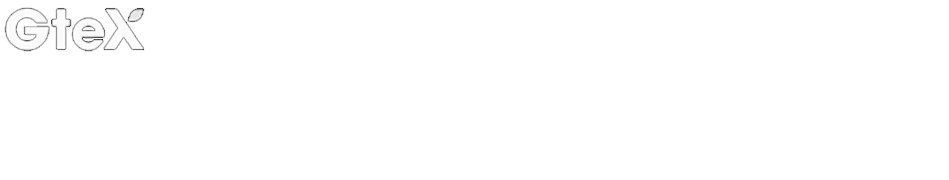10月31日(木)「社会課題解決に貢献する 微生物研究」バイオものづくり領域微生物中核チーム公開シンポジウム 開催致しました

2024年10月31日(木)に、大阪大学吹田キャンパス 銀杏会館3F 阪急電鉄・三和銀行ホールにて、「社会課題解決に貢献する 微生物研究」バイオものづくり領域微生物中核チーム公開シンポジウムを開催しました。
【主催】JST革新的GX技術創出事業(GteX)バイオものづくり領域微生物中核チーム
【共催】大阪大学生物工学国際交流センター/大阪大学先導的学際研究機構産業バイオ イニシアティブ研究部門
近畿バイオインダストリー振興会議/バイオコミュニティ関西BiocK
【後援】関西医薬品協会/日本生物工学会
【協力】大阪大学経営企画オフィス
本シンポジウムには、会場に98名、オンラインで173名の方々にご参加いただきました。
参加者からは、「直接、講師の先生に質問する貴重な機会を得られ、非常に有益な情報を得ることができました」(企業)や「微生物の世界を幅広い視点で見直すことができ、とても刺激になりました」(企業)といったご感想をいただき、多くの参加者の皆様からもご好評を頂戴し、盛会のうちに終えることが出来ました。
 開会あいさつ 尾上孝雄 (大阪大学理事・副学長(研究担当))
開会あいさつ 尾上孝雄 (大阪大学理事・副学長(研究担当)) シンポジウム概要説明
シンポジウム概要説明
本田孝祐 (大阪大学生物工学国際交流センター・教授) 基調講演
基調講演
「微生物統合データベースの可能性」
黒川顕 (情報・システム研究機構国立遺伝学研究所・教授 副所長)
セッション1「微生物でつくる」 「化学合成糖による有価物質のバイオ生産」
「化学合成糖による有価物質のバイオ生産」
中西周次 (大阪大学基礎工学研究科附属太陽エネルギー化学研究センター・教授) 「日本とインドネシアの発酵食品を基盤とするアップサイクル食品のバイオプリント」
「日本とインドネシアの発酵食品を基盤とするアップサイクル食品のバイオプリント」
境慎司 (大阪大学基礎工学研究科物質創成専攻・教授) 「新規タンパク質の人工設計」
「新規タンパク質の人工設計」
古賀信康 (大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質先端データ科学研究センター・教授)
セッション2「微生物をはかる」 「出芽酵母の代謝を計測し、活用する」
「出芽酵母の代謝を計測し、活用する」
松田史生 (大阪大学情報科学研究科バイオ情報工学専攻・教授) 「次世代プロテオミクスで微生物をはかる」
「次世代プロテオミクスで微生物をはかる」
青木航 (大阪大学工学研究科生物工学専攻・教授) 「対話型AIを用いたDNA配列設計の自動化」
「対話型AIを用いたDNA配列設計の自動化」
森秀人 (大阪大学世界最先端研究機構ヒューマン・メタバース疾患研究拠点・特任准教授(常勤))
セッション3「微生物でまもる」 「捕食性細菌とその様々な分野での活用可能性」
「捕食性細菌とその様々な分野での活用可能性」
井上大介 (大阪大学工学研究科環境エネルギー工学専攻・准教授) 「口腔微生物叢でまもる全身の健康」
「口腔微生物叢でまもる全身の健康」
久保庭雅惠 (大阪大学歯学研究科口腔感染制御学系部門・教授) 「皮膚マイクロバイオーム・病原細菌の解析とアトピー性皮膚炎への治療基盤創出」
「皮膚マイクロバイオーム・病原細菌の解析とアトピー性皮膚炎への治療基盤創出」
松岡悠美 (大阪大学世界最先端研究機構免疫学フロンティア研究センター・教授) 閉会あいさつ
閉会あいさつ
金田安史 (大阪大学理事・副学長(統括理事<大学経営、OU構想策定担当>)
●当日、時間の都合によりウェビナー内でお答えできなかったご質問につきまして、回答を掲載いたしました。ぜひご参照ください。
なお、本ページでは、掲載可能な質問への回答のみを抜粋しております。一部の回答は非掲載とさせていただいておりますのでご了承ください。
| 「微生物統合データベースの可能性」 黒川顕 教授 |
質問1 | データのオープンサイエンスとビジネスにはギャップがあることは指摘されていますが、先生はどのようにお考えですか? |
| 回答1 | 米国ではバイドール法によりデータ公開要求が法的要件として明確に規定されており、公的資金による研究データは原則公開が求められます。 一方、日本版バイドール条項は厄介です。データ公開義務を免除するものではないのですが、データ公開に関する明確な規定がありません。米国では、税金で得られたデータは皆が等しく共有することができ、そのデータから得られた新たな発見に対しては知的財産として保護される、という形になっています。したがって適正な競争が生まれ、ベンチャー企業も発展する訳です。日本はデータそのものを独り占めしてしまうので、独り占めした者が何ら発見できない場合、それらデータが死蔵してしまいます。 またオープンされないことで重複研究も出てしまい効率が悪いなど、多くの弊害を生み出しています。なかなか厄介な問題です。また是非議論させて頂ければと思います。 |
|
| 「捕食性細菌とその様々な分野での活用可能性」 井上大介 准教授 |
質問1 | 浄化槽投入でのデメリットはあるのでしょうか? |
| 回答1 | ご質問ありがとうございます。 捕食性細菌は活性汚泥などにも常在しておりますので、基本的には顕著に処理に影響する等はないものと考えております。 あり得るとすれば、過剰に溶菌した細菌の残骸がsCODとして流出することだと思いますが、まず起こらないものと思われます。 |
|
| 質問2 | ●面白いお話ありがとうございました。 捕食性の遺伝子はまだ不明化と思いますが、多様な細菌種で同様な捕食という行為が見られることからそれらの機能は水平伝播的機能と考えられますが、どうお考えですか? また、捕食性とはどのような環境状況で発動するのでしょうか?捕食細菌はエコシステムで優占種になり得るのでしょうか? ●細胞外に酵素を放出するとのことでしたが、どのような酵素なのでしょうか? |
|
| 回答2 | ご質問ありがとうございます。 表現型としては”捕食”という同一のものですが、捕食の基本的な機構自体が多様で、さらに、菌ごとに様々な加水分解酵素、二次代謝物を分泌する等で溶菌を行っています。そのため、必ずしも水平伝播的なものではないように感じております。 捕食機能の発現に関しては、通常の培地でも生育できる通性捕食性細菌の場合は、栄養枯渇が捕食機能のきっかけになります。偏性捕食性細菌の場合は、素早く動き回ることで餌を探し、何らかの方法で餌を認識すると捕食行動が開始される形です。何をもって認識しているのか?というところが不明で、重要な研究課題になると思います。 また、餌菌に依存して生きている偏性捕食性細菌が優占種になることはないですが、通性捕食性細菌として紹介したMyxobacteriaは土壌や活性汚泥では10%程度になることもあり、優占種になり得ます。 また、細胞外に分泌する酵素は、細胞壁を構成するタンパク質などを分解する多様な酵素になります。DNA分解酵素なども多数もっていることが報告されています。 |